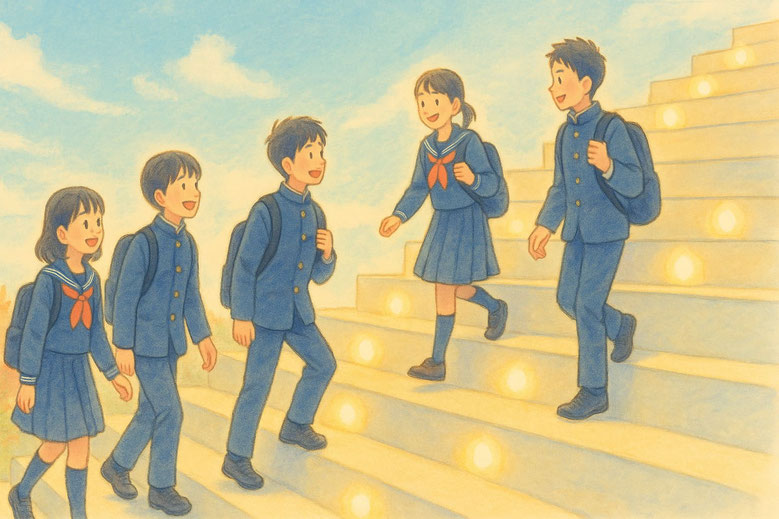
「どうせできない」を「やりたい!」に変えるには
こんにちは。Happy Education Lab.の宮脇です。
お子さんが宿題を前にして「やりたくない」「どうせできない」とつぶやくとき、親御さんとしてはすごく心配になりますよね。つい「頑張ったらご褒美買ってあげるよ」と言ってみたり、「やらなかったらスマホ禁止!」と厳しく言ってしまったり。
でも、心理学の研究を見ていると、こうした方法は一時的には効果があっても、長続きしにくいことが分かっています。
むしろ、子どもが「やらされている」と感じてしまうと、本来持っていたやる気まで奪ってしまうことがある。これはもったいないことだと思います。
では、どうすれば子どもは自分から学びに向かうのでしょうか。
答えのひとつは「内発的動機づけ」です。
つまり「知りたい」「できるようになりたい」という、心の中から湧き上がる気持ちですね。
新しい知識を得る喜びや、難しい問題が解けたときの達成感。
こうした感情こそが、学びの本当の原動力になります。
「できた!」の積み重ねが自信を生む
そして、その内発的動機づけを育てるカギになるのが「小さな成功体験」だと思っています。
いきなり高すぎる目標を与えてしまうと、失敗が重なって「どうせやっても無理」という学習性無力感に陥ってしまう。
これは切ないことです。
反対に、達成可能な小さなステップを区切って「できた!」を積み重ねていくと、「やればできる」という自己効力感が育っていきます。
この自己効力感こそが、子どもの学びを継続させる大切な力になるんですね。
例えば、数学が苦手な子に100問のドリルを渡すのではなく、まずは5問だけ。
それができたら「すごいね!」と認めてあげる。
そしてまた5問。
こうした小さな成功の積み重ねが、子どもの中に「自分はやればできるんだ」という感覚を育てていくわけです。
努力を認める言葉が未来を変える
ここで、大人の関わり方がとても重要になってきます。
同じ80点のテストを取ってきても、「すごいね、よく頑張ったね」と努力を認められた子と、「なんで20点も間違えたの」と責められた子では、その後の学習意欲はまったく違ってくるのです。
子どもの力を伸ばすのは「努力を見てくれる大人の存在」だと、私は思っています。
結果だけでなく、そこに至るまでのプロセスに目を向けた声かけをすることで、次への挑戦につながっていくわけです。
小さな変化を見逃さない
そして大切なのは、そんな小さなことにしっかり目を向けてあげることです。
以前は解けなかった問題が解けるようになった、宿題に取り組む時間が少し早くなった、ノートの字が丁寧になった。
ほんの些細な変化かもしれません。でも、こうした一つひとつの成長を見逃さずに認めてあげることが、子どもの「やればできる」という感覚を育てていくんです。
さらに、学びを日常生活と結びつけることも効果的でしょう。
算数の文章題を解くとき、「円を○個に分けると…」という抽象的な問題ではなく、「家族で旅行に行くときの予算を考えてみよう」にしてみる。
知識が生活とつながることで、子どもは「わかる!」「面白い!」と感じやすくなります。学びがぐっと自分ごとになっていくんですね。
今日の積み重ねが10年後の自信になる
勉強が「やらされるもの」から「自分からやりたいもの」に変わる瞬間は、こうした小さな積み重ねの中で訪れます。親や先生の声かけや工夫ひとつで、子どもは大きく変わるのです。
そして私が一番大切だと思っているのは、この「やればできる」という感覚を、今だけで終わらせないということです。
10年後、社会に出てからも「自分はやればできる」と信じて挑戦できる力を育てること。
これが、親として子どもに贈れる最大のギフトになるんじゃないでしょうか。
まずは、お子さんを見る、ということ。小さな変化を見逃さずに褒めてあげてください。
小さな成功体験を一緒に喜んで、努力を認めて励ます。
その積み重ねが、親子それぞれの未来の幸せにつながっていくのだと、私は信じています。
学びがぐっと自分ごとになっていくんですね。

【この記事を書いた人】
宮脇慎也(保護者向け教育コーチ)
・20年以上の教育現場経験
・700組以上の親子面談実績
・中学生の偏差値を平均7ポイント向上させた実績
・進学空間Move塾長として地域教育に貢献
・2030年までに1万組の親子の成長をサポートすることを目標
広島大学大学院社会科学研究科博士課程後期修了。2013年から広島市で学習塾を運営し、個別演習型指導で多くの生徒の学力向上を実現。近年はキャリア教育にも注力し、社会人講師を招いた講演会を多数主催。
Happy Education Lab. 運営者

コメントをお書きください